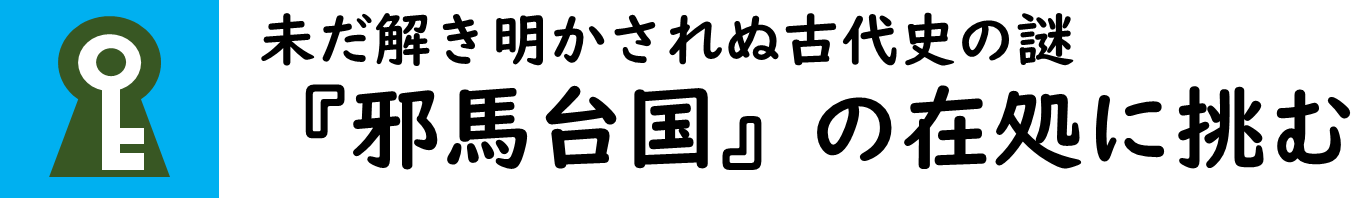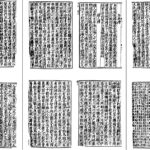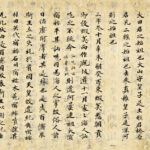サイト開設記念の第1弾は、5年に1度開催される五色神大祭へ出かけます!
前回の大祭には安倍首相が訪問したそうで私は今回が初めて(参拝は3度目)。日本最古の神宮と言われ神漏岐(かむろぎ)命・神漏美(かむろみ)命を祀ります。そんな神様は聞いたことがないと言う人も多いでしょうが古来より中臣氏が奏上する大嘗祭の寿ぎ詞や大祓の中で「皇親」として登場する神様なのです。
幣立神宮から古代文字の石板が見つかっています。表には「アソヒノオオカミ」と刻まれ、裏には「ヒフミ祝詞」が描かれています。「ヒフミ祝詞」の全文は「ヒフミヨイムナ ヤコトモ チロラネシキル ユヰツワヌ ソヲタハクメカ ウオエニ サリヘテノマス アセエホレケ」ですが、数え詞が入っていることに気づきましたか?
ちなみに神話や記紀に登場する「霊剣」で有名な奈良県・石上神宮の神拝詞にも「一二三四五六七八九十布瑠部由良由良止布瑠部」と入っているのですが、普段何気なく唱えている数え詞には実は私たちが忘れてはいけない大事なメッセージがわらべ歌「カゴメカゴメ」のように民間伝承として残ったのではないかと考えています。
「鯰」をめぐる熊本・謎解きの旅
その昔、阿蘇カルデラには湖水が広がっていたそうです。阿蘇の主神・健磐龍命が良田をつくろうとして阿蘇西側の立野の火口瀬を蹴破って湖水を抜こうとしたところ大鯰が横たわり水の流れをせき止めたため退治したと言う「蹴破り」伝承が残っています。「鯰」は「呉」国の眷属(神の使い)と言われています。邪馬台国は魏志倭人伝に登場しますが「魏」と敵対していた「呉」にまつわる伝承にはその在処の謎を解く鍵があるかもしれません。
また米どころとして有名な熊本県・菊池平野はその昔巨大な湖だったそうです。「鯰」は登場しませんがここにも「蹴破り」伝承が残っていたり、肥後~筑後にかけた有明海一帯には「鯰」にまつわる神社が点在します。有明海一帯には磐井の乱や埼玉県・さきたま古墳群と同じ鉄剣が見つかるなど古代史における重要なトピックスが数多く残されています。これまでの謎解き旅では十分な成果は得られませんでしたが今回は「鯰」をテーマに再挑戦したいと思います。